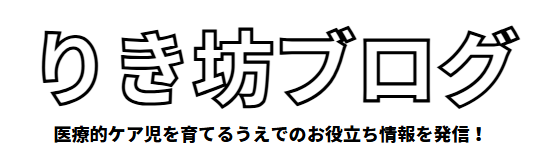みなさん、排痰補助装置ってどんな装置か知っていますか?
名前の通り、排痰を助けてくれる装置です。
普通の健常の子は、自分で「ごほん!」と咳をすることができますが、息子みたいな寝たきりの子などは、自分で咳をすることが難しいです。
その為、排痰補助装置を使って肺に痰がこびりつくのを防いだりしなければいけません。
痰がこびりつき、吸引機で痰が引けないくらいになってしまうと、サチュレーションが不安定になり、入院になる確率が高いです。
息子は今まで肺炎で何度も入院をしています。
毎日排痰補助装置をしていても、肺炎になるときはなってしまいます。
でもやらないよりは全然マシなので、排痰補助装置の使用は毎日のケアでかかせないです!
私が普段どんなふうに排痰補助装置を使用しているか、訪問看護さんから教えてもらったポイントを簡単にご紹介します★
お風呂あがりにする or 吸入後
排痰補助装置を使用する時は、痰を柔らかくしてからするのがポイントです!
もちろん、お風呂上りや吸入後でなくても効果は十分にあると思います。
息子は、必ずといっていいほどお風呂上りか吸入後に排痰補助装置を使用しています。
お風呂上りや吸入後に排痰補助装置を使用すると、とても痰が引けます★
まず最初に、水色のシート(パーカッションラップ)を胸の周りに装着します。
ポイントはきつく締め付けないで、こぶし1つ分余裕をもって装着することです。
装着が完了したらうつぶせにし、パーカッサーモードにしらたスタート★
胸に振動をあたえ、排痰の動きを促します。
体勢はうつぶせがいい!
息子みたいな寝たきりの子は、うつぶせになる機会があまりありません。
その為、痰が背中側に溜まりやすいみたいです。
なので排痰補助装置を使用する時は、うつぶせでしています。

なるべくうつぶせでしていますが、たまにうつぶせにすると嫌がったり、心拍が高くなり苦しくなる時もあるので、うつぶせが難しいときは無理せずに仰向けでしています。
健常な子だとうつぶせはとても簡単な体勢ですが、寝たきりの子にとってはとてもパワーを使う体勢です!
うつぶせにする場合は、様子を見ながら試してみて下さい★
胸に振動をあたえ終えたら、今度は咳をするモード(カフアシスト)にします。
息子は自分で咳をすることができないので、カフアシストで咳と同じ動作をしてもらいます。
よくおじさんたちが、「カーっ、ペ!」と痰を出しているのを見たことがあると思いますが、あんな感じなことを排痰装置がしてくれるイメージです!※説明が下手ですいません。
3方向(仰向け・右・左)でやり、手技と合わせる

ただ咳を促すだけでなく、スクイージングという手技を加えるとより効果的です!
スクイージングとは、痰が溜まっている部位に手を当てて、絞り込むように圧迫し空気を吐き出すときに、さらに圧迫を加えることによって溜まっている痰を移動させやすくする手技です。

カフアシストをしながら手技をやるのは最初は難しいので、もしパパなど手が空いているときは一緒にやってもいいかもしれません★
私は最初から頑張って一人でやりました☺♥
最後に
以上、息子のカフアシストのやり方をご紹介しました。
息子は1日2回、朝と夕方カフアシストをしています。普段は仕事をしている為、仕事がある日はデイサービスでお願いしています。
基本1日2回ですが、痰がゴロゴロしていたりサチュレーションがふらつくときは、1日3~4回しています。
1日3~4回してもサチュレーションがふらつくときは、だいたい肺炎で入院になってしまいます。
1回だけ入院せずに自宅で乗り越えたことがありますが、だいたい入院してしまいます。
あらためて、加湿の大切さを学ぶことができました。